こんばんは。
母親(生粋のミキプルーン信者)から
高濱正伸先生の子育てセミナー動画が送られてきました。
(ゲリラ的に)
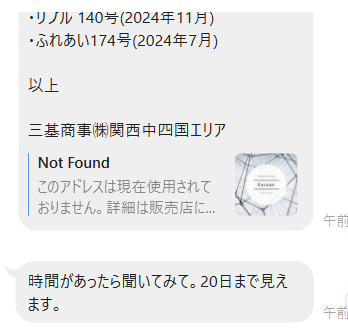

まさかミキプルーンに感謝する日がくるとはな
子どもの頃無理矢理飲まされ続けた苦い記憶……。
とっても有益だったのでみなさまにシェアします~~~!(はぁと)
まずはこれ知っておこう
目の前にいるお子さん、
いつまでも同じ生き物だと思ってませんか?
高濱先生曰くですね、
子どもの成長時期は大きく二つに分けられるそうです。

我が息子は5歳なのでまだイモムシです
このふたつの時期があるということを
認識しておくことが子育てにおいて
かなり重要なんですよね。
なぜなら、
イモムシの時期にすべき教育と
ちょうちょの時期にすべき教育は
全く違う!
イモムシの時期は葉っぱの食べ方を教えるのに対し、
ちょうちょの時期は飛び方を教えなくちゃいけない。
にも関わらず、
このふたつの時期に同じ教育をしてしまう親が多い。
つまりとっくにちょうちょになっているのに
いつまでもイモムシ気分で過干渉・口出しを続けるということです。
では各々どういう時期なのかを詳しく!
イモムシの時期
幼稚園や保育園・学校や習い事……
外でどんなに辛いことがあっても
家に帰ればお母さんがいて抱きしめて貰えれば
それだけで心の安定や支えになる時期
ちょうちょの時期

私は私!
という気持ちがまず芽生えます。
この時期に親以外の良き存在と巡り合うことが重要。
部活や先生、習いごとやバイトなど
干渉されたくない。

きたか……
この時期にやってはいけないことは
過干渉や口出しですね。
たとえば、
子どもに聞かれた質問に、親が答える
とかもう最悪の行為だそうです。
教育で最もひどいこと
それは「過干渉」だと高濱先生はおっしゃってました。
「過干渉は教育において最も残忍な行為(原文ママ)」

過干渉により、何の免疫もできていないまま
大人になると、すぐに心が折れてしまう。
ちゃんと傷付いて鍛えられることが大切!
その際に高濱先生がおすすめしていたのが
私も大好きなこちらの著書!
エミール 上 (岩波文庫 青622-1) [ ルソー,J-J. ]
ルソーという天才が書いた200年前の育児書です。
もちろん大昔なので今とは違う価値観の部分もあるんですが、
それでも現在まで語り継がれているには
理由がありますね……!
イライラしてるお母さん
高濱先生といえば花まる学習会ですよね。
たくさんの子どもたちを見てきたと同時に
たくさんの親たちも見てきている。
とにかく今は、外面は良くて、家の中ではイライラしているお母さんが多い、と。
家の中ではまるで蚊帳の外、というパターンだそうです。
高濱先生はこれまで非認知能力を伸ばす塾やら
キャンプやらを発案してきて、
これで子ども達を伸ばすんだと思ってやってきたそうですが、
この現状を目の当たりにした結果、
「【花まる」だけでは無理。家庭にメスを入れないといけない」
「お母さんの笑顔」これが全て
そもそも、なぜ今の母親たちはこんなにもイライラしているのか。
その理由として
よその子も一緒にみんなで子どもを育てた。
他人の赤子にお乳をあげてたりもしていたし、
子どもにイラッときてもすぐ話を聞いてくれる
「先輩ママ」が身近にいて「子どもってそんなもんよ~」と
宥めてくれた。
それがだんだん、「所有」という概念が広がりなくなった。
子育てって大変なのに、布おむつなんて使ってた時代の母親たちは
一体どうやって乗り越えてたんだろうかと考えたら
そういうことだったんだなって。
それが全て!!それが一番大事!

世の母たちよ、わがままでいい
大事なのは無理した作り笑いじゃなくて本当の笑顔ですから、。
みんなは何してる時がリフレッシュになる?
もしくは何してる時が苦痛?
これは私個人的な考えなんだけど、
前者も大事だけど、
実は重要なのって後者だと思ってて、
苦痛なことを排除したり、他の人に任せるだけで
だいぶ気持ちが楽になると思うんだよね。
自分が何をしたら笑顔になれるのか
考えるのと同時に、
何をやめたら楽になるのか
も一度じっくり考えてみてほしい!
高濱先生が見た「子どもを伸ばす親の特徴」
高濱先生曰く、
【子どもを伸ばす親】には共通点があるそう。
出身大学や職業は関係なく、
子どもが
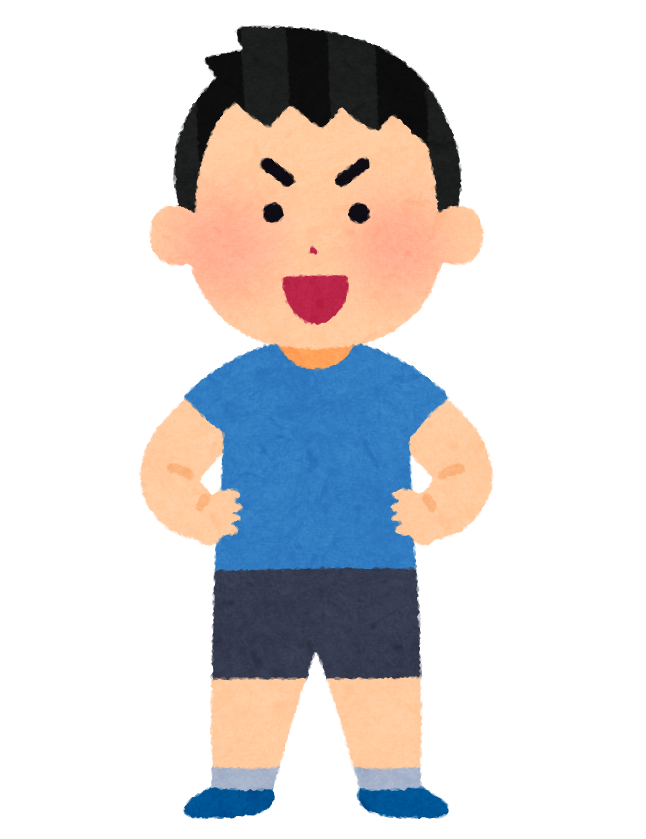
今日〇〇があって嬉しかったんだよ!
と話したときに……
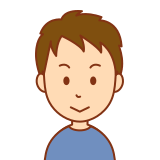
そういうときは「うれしい」じゃなくて「楽しい」って言うんだよ
そう答えたそうです。
それを聞いた時に高濱先生は
「これはデキる家だな…」
と思ったそう。

高濱先生にデキる家って思われるのご褒美すぎる
子どもの言い方に限らず、店員さんでもテレビでもなんでも
こうしたちょっとした言葉が
気になるか・気にならないか
そしてそれを
指摘するか・しないか
それがデキる親かそうでないか大きく分けるとのことでした。
そしてそれに繋がる話なのですが、
今「問いを読み取れない子」が増えているそう。
なぜなら
小さい頃からできていないから!
【子どもが伸びる家】
大人が聞いたことに対してちゃんと答えている。
言葉のキャッチボールがちゃんとできている。
【子どもが伸びない家】
たとえば
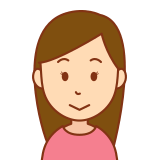
今日学校でなにしたの?

ていうかお腹すいた~
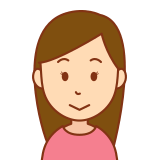
え、ていうかママも買い物行かなきゃ
みたいな!!
言葉のキャッチボールが適当になってしまっている家庭は要注意。
この「ていうか」私も無意識でよく使うので
ほんと気を付けなきゃ……。
あとは、
・親が頑張っている背中を見せる
・イキイキしている
なども大切なんだそう。
やるべきことをちゃんとやる子
by高濱正伸先生
まとめ
今回のセミナーで印象的だった話があって、
それが
画家の子は、全員集中力ある
という話。
これは遺伝というよりも、
小さい頃から親が没頭している姿を見ているので
親のやってる通りにやる、ということだそうです。
そして最初のほうの話になるんですが、
我々知育オタクはよく
「教育は3歳までが大切!」
と耳がタコになるくらい聞いてきましたよね。
でも高濱先生によると
教育で一番大事なのは11~18歳
だそうです。
それまでもいわゆる「イモムシ」の時期は、
どれだけこちらが怒っても、
次の日になったら「ママ~」と慕ってくれるのが子ども。
でもちょうちょの時期(11~18歳)はそうはいかない。
恨むし、暴れるし、甘くない。

私も親の番号着拒してましたねぇ…(淡い思い出)
みんなも色々と思い当たる節があるのではないでしょうか…
それだけ11~18歳は
取り扱い注意。
そうなると、ますます
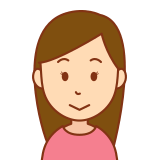
親として私がちゃんとしなきゃ!
と思いがちなんですけど……
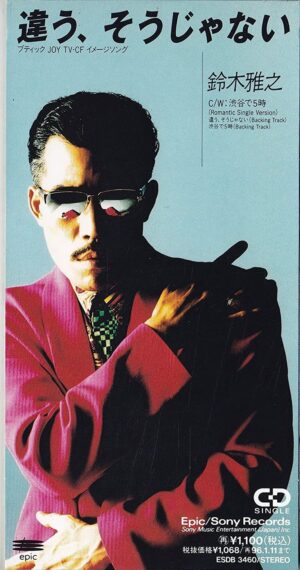
「私が」ではなく、
「誰に預けるか」
そこを考えるべきなんですって。
この時期の親にできることは
手を離して良い預け先を見つけること。
それが一番。
預け先というのは、部活とか習い事とか
そういう意味です。
幼児期と同じくらい青年期も大切、
それってこちらの本でも似たようなことを
言ってたんですよね。
【中古】15歳はなぜ言うことを聞かないのか? 最新脳科学でわかった第2の成長期 /日経BP/ロ-レンス・スタインバ-グ(単行本)
3歳までに大切なことも確かにあるけど、
それが全てである!
3歳までを逃したらやばい!!
だから〇〇をしなきゃ!!
というようなことを言って親を焦らせ
高い教材を売りつける教育界隈のおビジネスをみるたびに
「う~~ん」と思うこともありますが、
教育は長い目で冷静に見なければいけないなぁと。

というわけで大満足のオンラインセミナーでした
サンキュー!中井貴一!
(ミキプルーン=中井貴一)
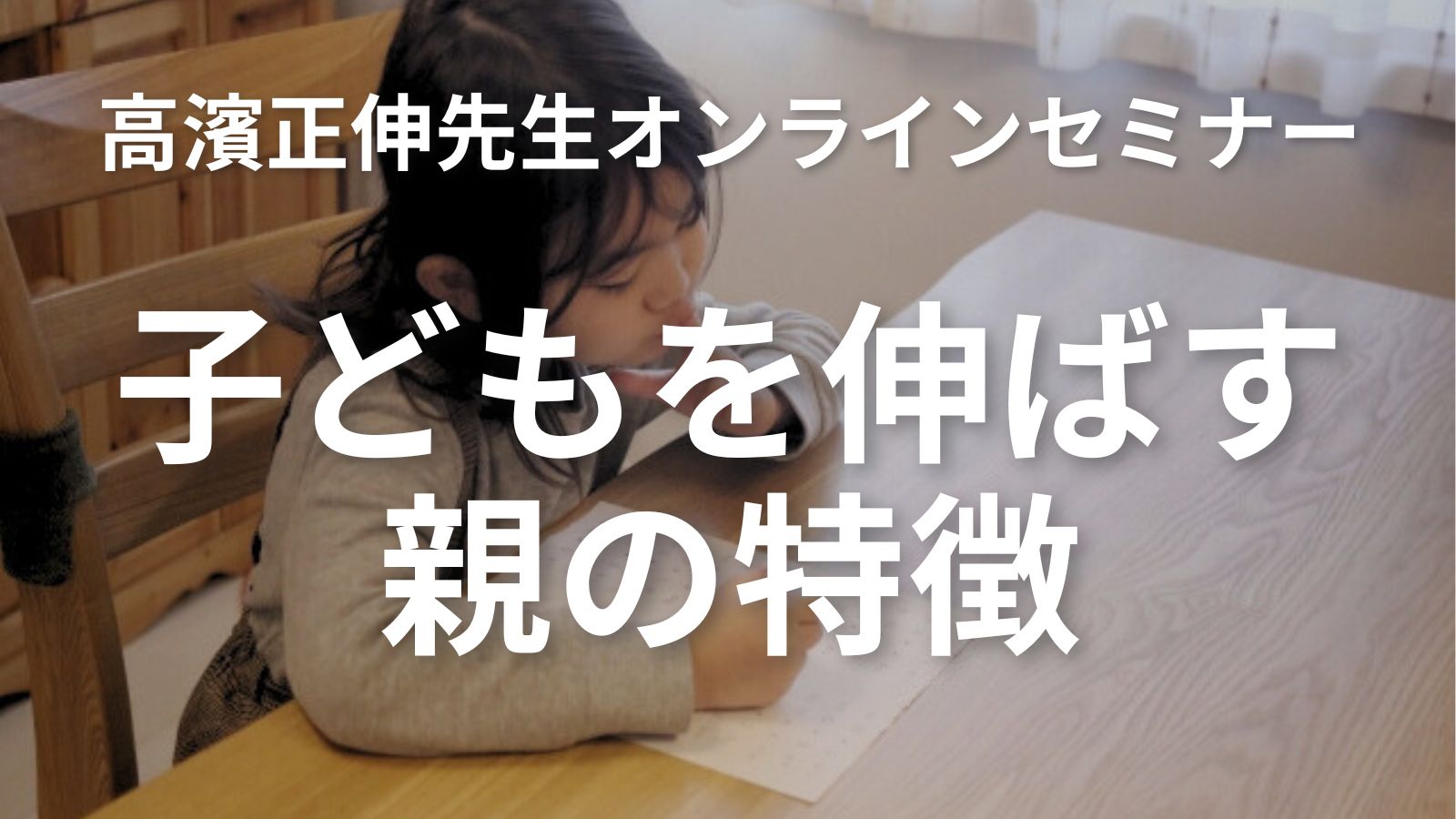
コメント