独身の時の私はとても不寛容だった。
電車で隣に座った子供の、泥の付いた靴が、
グレースコンチネンタルの白いワンピースをガシガシ蹴った時なんかは、
月間の不快指数の最高値を叩き出した。
色んな意味で、私はとても若かった。
その十数年後に出産し、初めて息子と二人で電車に乗った時、これは苦行だと思った。
初めて「公共の場における子供の大変さ」を理解した瞬間でもある。
今思えば息子は少々育てづらい子で、とりわけ電車のような密室ではいつもハラハラしていた。
電車に乗った途端、ギャー!と火が付いたように泣き喚く息子を抱っこして、
片手にベビーカー(乗ってくれない)と荷物を持ってドアの前で外を見せる。
「お外やで~」と必死で取り繕う私の顔面は汗だくで、
周りから白い目を向けられているかもしれないと思うと、怖くて他人の顔を見られなかった。
そんな時唯一できることと言えば
「できるだけ申し訳なさそうな顔をすること」
「一生懸命あやすこと」
だが、所詮周囲へのパフォーマンスに他ならない。
そんなことをしたって泣き止まないもんは泣き止まない、
なんて母親なら誰でも知っている。
赤ちゃんにキレる老人の真実
以前「電車内で赤ちゃん連れの夫婦にキレる高齢男性」の動画が
Xとネットニュースで話題になっていた。
赤ちゃんの泣き声がうるさいから黙らせろということである。
キレていたのは高齢男性一人で、車内にいた他の乗客が高齢男性に注意するが、
あろうことかその乗客にまで怒りの矛先を向けるという、
なんとも救いようのない内容であった。
なるほど。と私は思った。
これはリクルートメント現象ではないか。
私達の聞こえる音は、年齢によって変化する。
年齢が若いほど「高音」や「小さい音」を聞き取ることが可能だが、
加齢と共に聞き取れる音の周波数は変化し、
「高音」も「小さい音」も聞き取りにくくなっていく。
「低音」と「大きい音」に関しては聞き取ることができる。
つまり高齢者にとって赤ちゃんの泣き声は
「子連れが嫌い」とかそういうこと以前に、
実際に私達が感じるよりも「心身に不調をきたす不快な音」として伝わっている可能性が高い。
これは例えばAdoの「うっせえわ」という曲を聴いた時にも同じ現象が起こるらしい。
17歳(当時)のAdoの高い音域は、10~30代の人が聴いた時には特に不快感はなく、「ヒット曲」となった。
しかし特にサビ部分の音域の高さと怒鳴るような歌い方(それこそがこの曲の特徴であり魅力でもあるのだが)は、
50代以降の人にとって「不快な音」と伝わりやすい。
そして「最近の流行りの歌はうるさい」となるわけだ。
ちなみに私の実母は「うっせぇわ」よく聴いてた。(ファンキー)
赤ちゃんの泣き声は2,000Hz以上あると言われている。
対する60代以上の高齢者になると500〜2,000Hzの音が聞き取りにくい。
聞き取りにくい周波数から、
いきなり2,000Hz以上の周波数を感じると、
「急にハチャメチャにうるさくて不快」となるわけだ。
つまり、生物として、高齢者と赤ちゃんの泣き声の相性は最悪で、混ぜるな危険なのである。
もちろん高齢者に限った話ではない。
赤ちゃんに優しいお年寄りもたくさんいるし、
赤ちゃんに厳しい若者もいる。
(赤ちゃんというか子ども全般)
外国人観光客と私達
以前、とあるお笑い芸人の方が、新幹線のグリーン車に乗った時、
1歳にも満たないであろう赤ちゃんに向かって、
母親がひたすら話しかけている現場に遭遇した話をしていた。
「ずーっと喋ってんねん。オカンが」
「『あれ食べよっか』『あれ見てごらん』って。(赤ちゃんは)何もしゃべってへんで」
「1人が、ずーっと喋ってねん」
「しゃべれへん子やで。今まだ」
「家でやったらええやん。新幹線はそういう場所じゃないやん」
このニュースを読んだ時、このニュースについた賛同のコメント達含めて
「はぁ……そうですか」となんとも言えない感情になった。
子どもが泣いたりぐずったりしないように話しかけている
そのお母さんの気持ちが痛いほど分かるし、
何よりその芸人さんは子持ちだった。
それでもこの解像度なのだから、泣いたら泣いたで絶対文句言うんだろうなと。
「新幹線はそういう場所じゃない」
一体どういう場所なんだろう。
まさか、ゆっくり仮眠を取ったり、パソコンで仕事をするための場所だとでも思っているのだろうか。
ただの移動手段なのに。
去年のことである。
岐阜旅行の帰り、大雪で乱れていた特急電車になんとか乗ったら、
私たち家族以外、全員外国人観光客という奇跡の車両にでくわした。
それでどうなったかというと、
驚くほど快適だった。
そこでは誰もが通常トーンの声量で自由に話し、
外国人家族の子供たちもウロウロし、
私たちもウロウロした。
というのも大雪の影響で通常よりもゆっくり走っていたし、
何度も緊急停止を繰り返していた。(しかもなかなか進まない)
いつ大阪に着くか全く見通しが立たない状態で、
4歳の息子に何時間も、
「じっと座ってなさい、静かにしなさい」は到底無理があった。
子連れとして、あんなにも快適な車内空間は未だかつてなかった。
通路を挟んだ隣は中国人カップルだった。
車内放送の日本語を聞き取れなかったのか、困っていたので夫が通訳していた。
お礼にお菓子をくれた。
なかなか動かない電車。
私は立ち上がって歩いたり、
歩きながらストレッチをしたり、
歩きながら鼻歌を歌ったりした。
彼らは一切意に返さなかった。
彼らは彼らで、各々が最もリラックスできるスタイルで
誰が文句を言うでもなく、ゆったりと過ごしていた。
息子と、窓の外の雪景色を見てはしゃいだりもした。
やはり誰も気にしていなかった。
なんて楽なんだろう。
大雪でいつ到着するか分からない電車。
本来イライラするはずなのに、何なんだ、この寝台特急ななつぼしに乗ったかのような居心地の良さは。
(まぁななつぼし乗ったことないけど)
楽しい旅行の締めくくりにふさわしい最後だった。
これがもし、周りが全員日本人の乗客だったらきっとこうはいかなかったと思う。
もちろん鼻歌も歌わないし、ストレッチをすることもなく、
ぐずる息子を静かにさせなければ、迷惑になってはいけない、と
あの手この手を尽くして疲弊していたのではないだろうか。
(ちなみに今回の話に他意は一切ない。
今色々と問題視されている外国人による治安悪化やオーバーツーリズムの問題などとは切り離して読んで欲しい)
つまりなにが言いたいかと言うと、
日本は他国に比べ、とても清潔だし、マナーも良く、基本的に静かである。ということ。
電車は時間通りに来るし、観光地のトイレだっていつも綺麗。
私達は当たり前にそれらを享受している。
私が日本を好きな理由はまさにこれだし、
こんなに整っていて、清潔な国で子育てができることも幸せだと思う。
が、日本はそれと引き換えに、そこから逸脱する者を激しく非難する傾向にある。
電車が数分遅れた時、駅員を罵倒するおじさんを何度も見たし、
他国ではOK(な国が多い)電車内の通話や会話だって、日本ではマナー違反。
美術館に子どもを気軽に連れてはいけない。
公共の場で赤ちゃんは泣かせないように努力しないといけない。
だって不快な人もいるから。
と、個人の「不快である」という理由がわりとどこでもまかり通ってしまう。
あらゆる場所で静寂を求め、
ボール遊び禁止、
公園で大声出すの禁止
などの過剰なクレームがきたり、
SNSにお庭プールの写真を載せるだけで
「近所迷惑(妄想)子どもの声は騒音」などというコメントがつく国である。
なので日本の電車もいつも静かで、働く大人にとってとても都合が良い。
そんな、「大人を快適に過ごさせるための空間」に子どもが入ればどうだ。
前頭葉が未発達で、「空気を読む」という機能が備わっていない子供の登場により、
「こっちは仕事で疲れてるのに」
「親が申し訳なさそうにしてればまだ許せる」
「満員電車の時間帯は子連れは乗るな」
「飛行機に赤ちゃん連れなんて迷惑」
そんな上から目線な意見がよく出てくるのも全て、
「働く大人を快適にさせてこそ、日本社会」
という暗黙のルールがあるからではないか。
この国は常に「大人が不快に思わないかどうか」にフォーカスを充てて作られている。
とはいえ、私だって子どもを産むまではそんなこと分からなかったし、
「大人が快適に過ごせる空間」にありがたくあやかっていたのも事実。
出生率は9年連続過去最低を記録していて、
「子持ち」はますますマイノリティになっていき、
ますます肩身が狭くなる。
そんな時代に子どもを育てている自分って、一体なんなんだろう
そう思うこともある。
一生懸命子育てしていても、
「清潔で静かでマナーの良い素敵な我が国」
において、子どもは異物であり、優先されようもんなら
「でたでた(笑)子持ち様(笑)」
と揶揄されかねない。
「大人に迷惑を掛けないのならまぁ存在してても良いよ」
程度の認識なのがとても悲しい。
それでも、電車で、バスで、乗り合わせたエレベーターで、
優しくしてくれる人はいる。
子どもに優しく微笑みかけてくれる。
それだけで、「今日出掛けて良かった」と思えるのだ。
そんな風に与えてもらった優しさは、自分も誰かに還元したい。
ほんの2,30年も経てばいずれ私も老いがくるのだけど、
「赤ちゃんの泣き声が心身に不調をきたす音」
になってしまって苦しい時がくるかもしれない。
頭では仕方ないと分かっていても、
身体が受け付けないというのはよくあること。
そんな時のために高性能のノイズキャンセリングを買おう。
子どもを排除しようとするのではなく、自分が別の車両に移ろう。
自分の子育てが終わっても、
私達だけは次の世代に優しくありたいと思う。
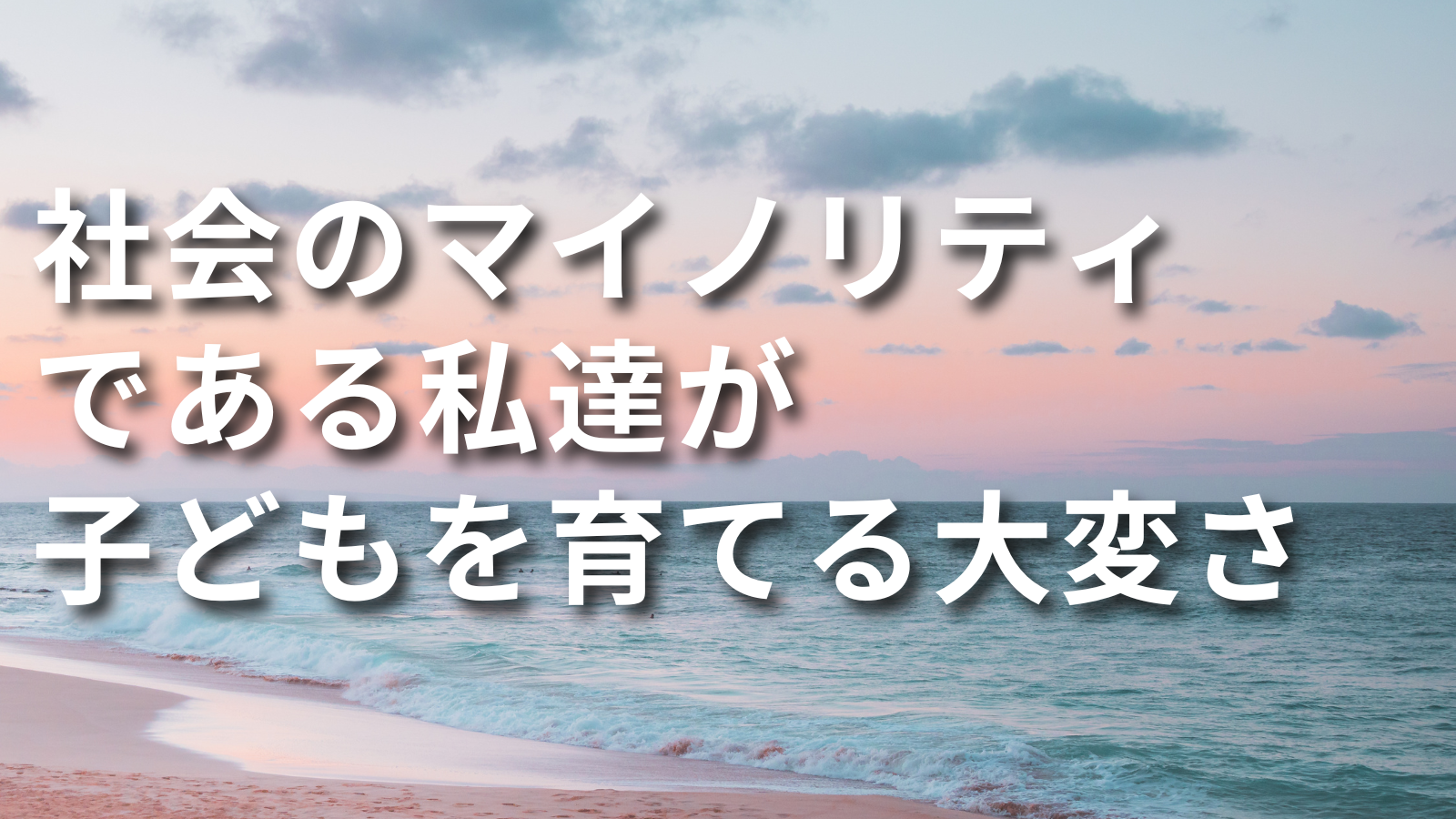
コメント